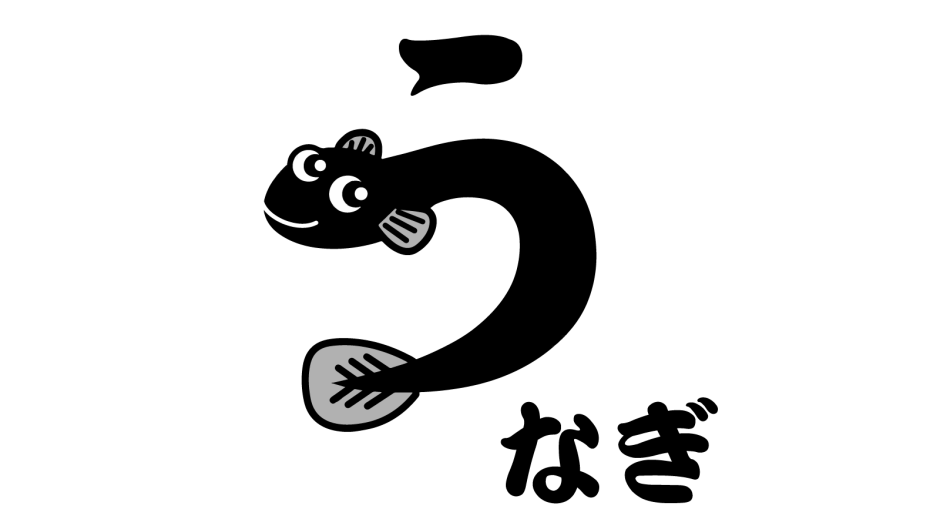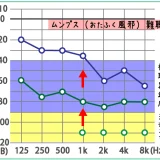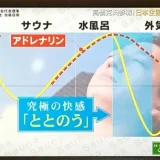ともろです
少し早い話題ですが、昔から土用の丑の日には鰻を食べる風習があります。
テレビ番組でも取り上げていますが、土用の丑に鰻を食べる風習の起源は遡ること江戸時代、エレキテルで有名な平賀源内が
友人に相談を持ちかけられたこと、鰻は夏になると売れ行きが悪くなる、何とかして売りたいと友人、そこで源内に妙案が浮かぶ、「丑の日だから、『う』のつくものを食べると縁起が良い」という語路合せを思いつく。同時に「精のつく鰻は夏を乗り切るのに最適」というセールスポイントを加えた。と言われています。
そもそも土用とは、季節の変わり目をあらわし、年に4回あります。
- 立夏の前である春の土用
- 立秋の前である夏の土用
- 立冬の前である秋の土用
- 立春の前である冬の土用
の4回です。
そして土用の土とは、呪怨~感情と臓器でも少し書きましたが、東洋医学でいうところの「脾」という臓器に属し
湿気に影響を受けます。そのため、湿気の多い時、季節の変わり目には体調を崩しやすくなります。具体的には、脾の働きが悪いと食欲不振、下痢、むくみ、だるさなどの症状があらわれます。
もともと日本は島国で、湿気の多い風土なため、湿気によって脾が弱りやすい民族です。梅雨入りしてから
土用の丑である7月25日頃、脾の働きが弱らないようにしましょう。
ここでやっと本題の鰻です。脾の働きを高めるには鰻ではありません。鰻はビタミンAとDが多く含まれ、精のつく食べ物ですが、まずは脾の働きを高め、胃腸の消化吸収機能を高めることが必要です。そして、その答えの一つに「足三里」というツボがあります。
鍼灸治療では、患者さんの体質に合わせて「今」体に必要なツボを選択します。

家庭では足三里を刺激しましょう。足三里の場所は、膝の下でスネの外側にあります。
でも三里について紹介しましたが、
- 足三里の場所を詳しく知りたい人
- 夏バテしやすい人
- 冷たいものばかり飲食する人
- もともと胃腸が弱い人
は鍼灸治療をお試し下さい。ちなみに私は鰻大好きです。鰻は食べたい時に食べます。
以上